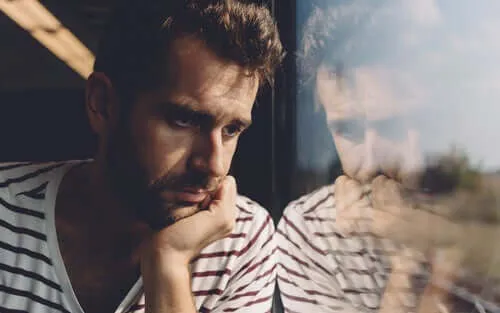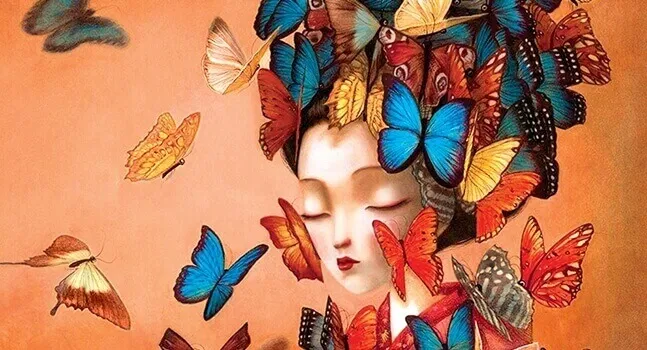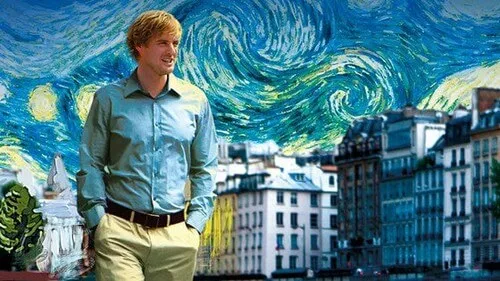あなたは他人の話を聞く方法を本当に知っていますか、それとも相手の言葉の感情的な内容を考慮せずにただ相手の言うことを聞いているだけですか? 効果的なコミュニケーションには積極的な傾聴が不可欠です .
積極的な傾聴のスキルはさまざまな方法で定義されますが、次の 2 つの要素が欠けてはなりません。 の 理解 そして注意 。これらがこのスキルの主な特徴です。
積極的に話を聞くとき、私たちは相手が私たちに伝えたいメッセージを理解することにリソースのほとんどを費やします。また、私たちは対話者に、彼が私たちに伝えたいことについての私たちの理解を伝えます。 したがって、心理的に対応できるか、話しかけてくる人のメッセージに注意を払うかが問題となります。 .
積極的な傾聴の反対は、気を散らした傾聴です。私たちは物理的にその場にいますが、心は対話者が私たちに伝えていることよりも別のことを優先します。これは、私たちが彼の言っていることが重要であるとは考えていないことを意味します。その結果、相手のメッセージを完全に理解できないリスクがあります。この意味で 積極的に傾聴することは、とりわけ、共感力を高め、他の人の感情を理解するのに役立ちます .

現代におけるコミュニケーション不足の主な原因は、話を聞くことができないことです。私たちは、相手が何を言っているかよりも、自分が介入したり、自分の意見を主張したりすることに夢中になります。ここではコミュニケーションの本質が失われます。私たちは、聞くことが自動的に行われるプロセスであると誤解していますが、そうではありません。 聞く 話すときよりも多くの努力が必要になることがよくあります .
他人の話を本当に聞きたいなら、言葉を超えなければなりません
私たちは通常、言語の重要性を認識していますが、他者とのコミュニケーションの 65 ~ 80% は非言語チャネルを通じて行われます。コミュニケーションを効果的に行うためには、音声と非言語的表現の間に一貫性があることが理想です。この意味で 積極的な傾聴にも類似点があります。相手が自分の話を聞いてくれていると感じることと同じくらい、聞くことが重要です。 .
このスキルでは、話し手の視点からコミュニケーションを聞き、理解することが必要です。言い換えれば、それは直接的に表現された言葉だけでなく、その言葉が隠している感情、考え、思考にも耳を傾けることの問題なのです。 必要があります 共感 つまり、相手の立場に立って、相手の気持ちを理解しようとすることです .

非言語言語は、私たちが他人や自分自身に対してどのように行動したり反応したりするかについてのものです。言葉を超えて聞くということは、聞いたり見たりしたものを理解し、意味を理解することを意味します。 目の前の人をあらゆる次元で理解するということは、彼の言葉に興味を持って耳を傾けずに、彼の言うことすべてに同意することを意味するものではありません .
積極的に傾聴することが孤独に対する最良の治療法である
ほとんどの人は聞くよりも話すことを好みます 。私たちが自分自身のことを話すとき、私たちは喜びに関連する脳の領域を活性化するので、ある時点で他人ではなく自分自身の話を聞きたいと思うのが普通です。
デール・カーネギー 他人にどう接し、彼らと友達になるか 。それは実際には、人々の間の関係を改善するための哲学と方法を例示した論文でした。カーネージはこう主張した の 共謀 積極的に傾聴することで確立され、人間関係にプラスの影響を与える 新しいものを生み出し、既存のものを強化します。
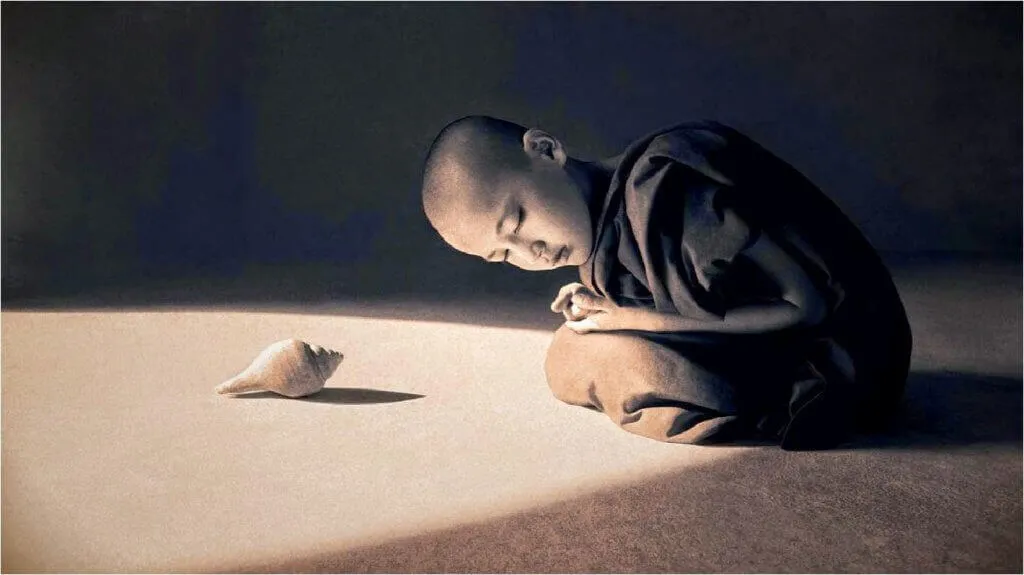
他者の意見に積極的に耳を傾けることで、共謀関係が蔓延するソーシャルネットワークを構築できる可能性が得られます。相手の話を聞き、自分たちが何をしていたかは脇に置いて、たとえそれが私たちにとって無関係または間違っているように見えても、対話者の言葉に注意を払う それは彼がありのままの自分を表現できるようにする方法です .
私たちが相手の話を遮ることなく注意深く耳を傾けると、彼は安心して私たちに吐き出せるようになり、彼が最も誠実な感情を明らかにできるようになります。 ほとんどの場合、必要ありません 意見 .
私たちには、何もせずに人々を助ける力があるのに、それに気づいていないことがよくあります。他の人の意見に耳を傾ける方法を知るという賜物により、私たちは相手をより深く理解し、絆を強め、前向きな関係を築く可能性が高くなります。この意味で、私たちが与えるものは私たちに影響を与えます。 たとえそれが私利私欲であっても、積極的に耳を傾ける価値があります .
参考文献:
- バーリー アレン M. (1996) 聞くことを学ぶ フランコ・アンジェロ・エディション。
- モリーノ A. とティツィアーノ F. (1996) 聞く技術 – 自分の話を聞くために他人の話を聞く マグナネッリ・エディターレ。
- ゴードン T. (1991) 有能な教師 関節。
- リス J. (2004) 深く聞く モルフェッタ日時計。
- ラス・P. (2017) 聞く技術 イル・プント・ディンコントロ・エディツィオーニ。
- スクラヴィ M. (2003) 傾聴の芸術と可能世界 – 私たちがその一部となっている枠から逃れる方法 ブルーノ・モンダドリ出版社。
- ステラ R. (2012) マスコミュニケーションの社会学 UTET大学。